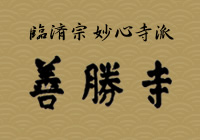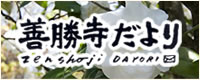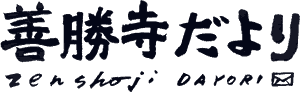 |
善勝寺だより 第83号平成25年6月24日発行発行責任者 明見弘道 (1ページ) |
 |
|---|

五月下旬から六月にかけて境地区の農家の方は活気に満ちあふれています。もちろん田植えで忙しいのですが、顔つきがいきいきとして見えます。鳥もカエルも、草木全てがいきいきと輝いてみえ、私はこの時期が好きです。(雑草のいきいきにはうんざりしますが…)
お寺も、お盆モードになるのはこの時期であり、そのスタートとなるのがこの「善勝寺だより」の発送です。
檀信徒の皆様におかれましても、それぞれの営みに励んでおられることとお察し申します。
以前、牧師さんで北九州ホームレス支援機構の理事長をされている、奥田知志さんの講演集を読みました。考えさせられることが多々ありましたのでよく覚えていたのですが、6月14日の読売新聞に掲載されていましたので紹介します。
一面のタイトルは『老後悠々気づけば独り』。これに関連した六面の記事を紹介します。
“私たちの支援は路上生活者に対して、食べ物を渡し、アパートに住んでもらうことから始まった。ある日アパートに入居した元ホームレスの高齢男性を訪ねると、部屋にぽつんと座っていた。そこには路上と変わらない孤独があった。以前は「畳の上で死にたい」と言っていた男性が、「最期は誰が看取ってくれるのか」と問うてきた。
単に食料や家があっても問題は解決しない。人間らしく生きるには人とのつながりが必要だと痛感した。
元ホームレスの高齢者は、援助されるだけの生活を続けるうち、元気を失っていった。そこで、「仲間の会」を作り、サークル活動や自宅訪問、仲間の葬儀などを、自分たちでやってもらうことにした。互いに支え合う関係ができると、彼らは元気を取り戻していった。
人は誰かのために生きる存在だ。助けられた人も、助ける側になることで、「自己有用感」を取り戻せる。孤立した高齢者のため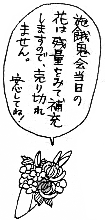 、各地で見守り活動が行われているが、同時に相互に支え合う関係作りも進めるべきだと考える。
、各地で見守り活動が行われているが、同時に相互に支え合う関係作りも進めるべきだと考える。
「無縁社会」などと言われるが、全ての縁が消えたわけではない。細った縁をつなぎ合わせる仕組みが必要であろう。”
以上、『衣食住だけでは孤独のまま、細いつながり支援の糸口に』というのが奥田理事長の意見です。
善勝寺の檀家さんの内にも、「葬義は家族だけで行いたい」という方が増えつつありますが、血縁・地縁・仕事の縁と、多くの方と関わりをもって、支えられて生きてこられたわけです。できる限り多くの方々にお知らせし、喪主の方が故人に成り代わってお礼の挨拶するのが葬義だと思います。
そういった縁を自ら切るようなことをすると、自ら孤独を呼ぶことにつながるのではないでしょうか。
最後に、季節柄ご自愛下さいますよう念じ申し上げます。
明見弘道
- 【善勝寺だよりトップへ】
- 【次のページへ】